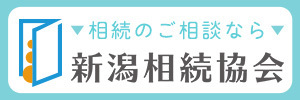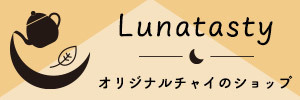三条市の会計事務所、L&Bヨシダ税理士法人です。

三条市・見附市の確定申告・決算申告はご相談ください!
L&Bヨシダ税理士法人(三条市オフィス)
〒955-0081 新潟県三条市東裏館2-14-15
アクセス:東三条駅から車で7分
営業 時間 | 平日9:00 ~17:30 |
|---|
定休日 | 土、日、祝日 |
|---|
社葬の流れや経費の範囲
突然社長が倒れたり、会社に尽くしてくれた社員が亡くなったりしたら、その葬儀を社葬にするよう議論が起こるかもしれません。
社葬とは「会社で手配するお葬式」のことです。会社に貢献してくれた人に対して、会社が儀礼を尽くします。
今回は社葬の流れや、経費の計上などについて解説いたします。
経費にできる範囲や準備等を知っておき、来るべき日に備えましょう。
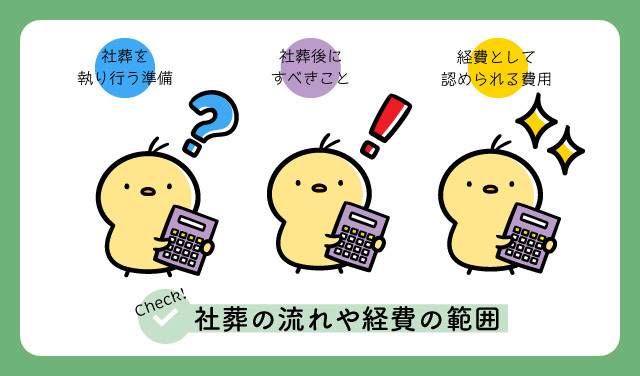
社葬を執り行う前段階で確認すべきこと、やるべきことを下記にまとめます。
会社として社葬を執り行うかを話し合い、遺族の意思を尊重した上で実行するかを判断します。
社葬と一般葬の違い
まずは社葬と一般葬の違いを知っておきましょう。
社葬とは、会社が主体となって執り行う葬儀です。
一般的にはご親族による密葬が先に行われ、その後で社葬となります。
事前の密葬はご親族主体で執り行われるもので、会社関係者はあまり参加しない傾向にあります。
一方で、一般葬とは、ご親族が主体となり執り行う葬儀です。通常思い浮かべる葬儀の形式です。
家族経営の中小企業の場合、社葬と一般葬を足した「合同葬」もよく執り行われます。
合同葬とは、ご親族と会社が一体になって葬儀を執り行う形式です。
通常は葬儀の経費をご親族と会社で折半するため、双方の金銭的負担が抑えられます。
社葬にすべき人か確認
会社で「社葬取扱規定」等を定めている場合は、その規定に則り社葬すべき人かを判断してください。
社葬規定がない場合は、会社に大きく貢献した役員や、業務中に亡くなった社員等が該当します。
【社葬にすべき人の例】
創業者、会長、社長、表彰対象者、業務中に亡くなった社員、業務中の怪我が原因で亡くなった社員 等
臨時取締役会の開催
社葬を執り行うかどうかを臨時取締役会で決定します。
この時、亡くなった人の周知や今後の動き等についても決めておきましょう。
また、社葬にどの程度の金額を負担するのかを決めます。
地域や会社の規模、列席者数にもよりますが、300〜500万円前後になることが多いようです。
予算も検討しながら葬儀社を選定してください。
臨時取締役会の議事録は、社葬費用を経費計上するために必要です。必ず議事録を残しましょう。
遺族の意思確認
ご遺族やご親族に対して、社葬の許可を得ましょう。
故人を最も悼んでいるのはご遺族やご親族ですので、必ず意思の確認を行ってください。
基本的にはご遺族やご親族の意思を尊重します。
仮に社葬を辞退された場合は、葬儀とは別に「お別れ会」を開催する等で対応しましょう。
お別れ会とは、葬儀とは異なるお別れの場です。特に著名人が亡くなると、ファンの方を対象としたお別れ会が数多く催されています。
お別れ会は宗教色が薄く、多くのケースではホテルの会場やレストラン等で執り行われます。
社内外への通達
社長や社員が亡くなったこと、社葬を執り行うことを周知します。
社員には、対外的にどのような対応をするのかも伝えましょう。
また社葬の案内状を送る取引先をまとめあげ、速やかに送付します。
その際には、供花や供物、香典等を受け取るのか、何をどこまで辞退するのかを決めて案内状に盛り込みましょう。
香典については社葬後の会計処理が複雑なこともあり、辞退するケースがほとんどのようです。
同時に、新聞に訃報記事を載せる場合はその手配もします。
担当者を決める
葬儀委員長を選定します。
葬儀委員長は葬儀社と連携して、社葬の準備や当日の打ち合わせを行う役職です。
主に後継者が担当します。会社の規模や考え方によっては、人事部長等が担うケースもあるようです。
葬儀業者との打ち合わせ
葬儀業者と打ち合わせを行います。
以降の流れややるべきことは、基本的に葬儀社がリードしてくれます。
会社側がするのは、葬儀社から提示された選択肢に対して「どれを選択するか」「オプションをどれだけつけるか」「その担当者を誰にするのか」等を決めることです。
決めるだけとはいえ、式場のレイアウトから誘導員の人数や位置、弔電への対応等、様々な内容について精査しなければなりません。当日まで気を抜けませんのでご注意ください。
予算から大きくはみださないよう注意しながら、故人と列席者に失礼のない葬儀となるよう充実させてください。
葬儀当日の流れ
社葬当日も、基本的には葬儀社がリードしてくれます。葬儀社に従いながら葬儀を進めていきましょう。
以下に例を掲載しますので、参考にしてください。
ただし宗教や会場等の違いにより、当日の流れは大きく異なります。あくまでも参考としてご覧ください。
| 式開始前 | 2〜3時間前に集合。役割の再確認 |
|---|---|
| 遺骨と位牌の到着。ご安置 | |
| ご遺族やご親族到着。控室に移動 | |
| 受付開始。来賓や弔辞者到着。式場入場 | |
| ご遺族等式場入場 | |
| 導師入場 | |
| 式進行 | 開式の辞 |
| 読経 | |
| 弔電奉読 | |
| 喪主の挨拶 | |
| 焼香 | |
| 導師退場 | |
| 閉会の辞 | |
| 式終了 | 香典返しとお見送り |
弔電等の整理
届いた弔電はリスト化しておきましょう。
その他弔問者リスト等の文書も整理して残しておきます。
返品等の送付
供花や供物をいただいた場合はリスト化して返礼品を送付します。
葬儀社が目安となる品物を見繕ってくれますので、予算オーバーにならないよう気をつけながら選定し、送付してください。
各種支払い
葬儀社や式場等への支払いを完了させます。
経費計上しますので、必ず領収書を受け取ってください。
領収書を整理して、会計報告書にまとめます。
故人の退職金計算や保険等の精算
年度半ばで亡くなった場合、その時点までの給与や退職金を計算し、源泉徴収票を発行しなければなりません。
故人の源泉徴収票を元に、遺族が故人の準確定申告を行うためです。
給与と退職金の計算
就業規則に基づいて給与を計算し、支払いを行います。
なお最終給与計算における税金や保険料については以下のとおりです。
| 所得税 | 死亡日以降に支給される給与からは天引きしない。 |
|---|---|
| 住民税 | 死亡日以降に支給される給与からは天引きしない。以降の住民税は相続人が納付することになる。 |
| 雇用保険料 | 最終給与から1カ月分を天引き。 |
| 健康保険料や厚生年金保険料 | 多くの場合は死亡日の前月分給与まで天引き。給与計算方法や死亡日により異なる。 |
給与の受取人は、原則的には法定相続人です。
亡くなった人名義の銀行口座等は、原則として凍結されます。
最後の給与を振り込もうとしても振り込めないかもしれません。ご注意ください。
死亡退職金を支払う場合は、その金額も計算します。死亡退職金も、原則として法定相続人が受け取ります。
源泉徴収票の発行と準確定申告
最終給与を含めた総支払額を算出し、源泉徴収票を発行します。
発行される源泉徴収票を元に、ご遺族は準確定申告を4カ月以内に行わなくてはなりません。
会社は速やかに源泉徴収票を発行し、ご遺族に送付しましょう。
埋葬料または葬祭料の請求
埋葬料とは、協会けんぽ等の被保険者が亡くなった際に給付されるお金です。埋葬を行う人が受給できます。
社葬を執り行ったとしても、ご遺族が密葬等を行っている場合はご遺族に給付されます。
個人事業主が亡くなった場合は、埋葬料ではなく葬祭費が受け取れます。葬祭費は国民健康保険から支給されます。埋葬料も葬祭費も大差はありません。
葬祭料とは、業務上の災害で亡くなった場合に労災保険から支給される給付です。この場合は、健康保険組合や国民健康保険からの埋葬料や葬祭費は受け取れません。労働基準監督署に対して葬祭料の請求を行いましょう。
被保険者資格喪失手続き
- 健康保険や厚生年金保険、雇用保険の「被保険者資格喪失手続き」
- 住民税の「給与所得者移動届出書」提出
- 健康保険証の回収または回収不能届の提出
会社はこれらの作業を行います。
社葬で経費にできる範囲は、法人税法 基本通達9-7-19にある「社葬のために通常要すると認められる部分の金額」によって定められています。
解説すると「社葬を行うことが社会通念上相当」かつ「社葬のために通常要すると認められる費用」ならば、福利厚生費として計上できるとするものです。
「社葬を行うことが社会通念上相当」とは、上記で解説したとおり会社への功労者等に対する社葬であることです。
そして「社葬のために通常要すると認められる部分の金額」には、一般的に下記のようなものが挙げられます。
なお社葬で会社が受け取った香典は、課税対象となります。
しかし社葬であっても、ご遺族が受け取った場合は非課税の扱いになります。
会計処理が面倒ならば、香典を辞退するかご遺族にお渡しするのが良いでしょう。
経費として認められる社葬費用の例
- 式場使用料
- 祭壇や生花といった装飾料金
- 音響や照明等の設備使用料
- ご遺族や来賓等の送迎にかかる費用
- 警備員や誘導員等の人件費
- お布施
- 飲食費
- お礼状や返礼品費用
- 社葬案内状の作成や郵送代
経費として認められない社葬費用の例
遺族が負担すべきとされている費用は、会社の経費として認められません。会社が負担した場合、これらは臨時給与として取り扱われます。
- 社葬以外でかかった費用(事前の密葬費等)
- 香典返し
- 火葬料
- 位牌等の料金
- 法事の費用 等
社葬とは、会社が執り行う葬儀の一種です。他に合同葬やお別れ会等の形式を用いることもあります。それぞれ特徴が異なりますので、どのような葬儀にしたいのか考え、ご遺族と相談して決めてください。
社葬を執り行う場合は、多くの人が一致団結して速やかに進めなければなりません。本記事を参考に、落ち着いて行動しましょう。
可能ならば、社葬の必要性が出る前に、社葬取扱規定を作成しましょう。
金額等の取り決めが事前にされていれば、社葬決定後に動きやすくなります。
社葬の費用がどこまで経費にできるのか、社葬規定の作成方法が分からない等、お困りごとがあれば、顧問税理士にご相談ください。
- 依頼の手引き
- 事務所紹介
- お役立ち情報
事務所概要

L&Bヨシダ税理士法人(三条市オフィス)
〒955-0081
新潟県三条市東裏館2-14-15
アクセス:JR東三条駅から車で7分
TEL:0256-32-5002
主な業務地域
新潟県三条市、見附市など